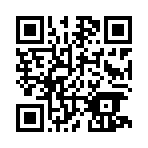2020年02月17日
足の小指が……
御座敷でお料理を提供していた時に…
九代目に惨事が起こりました!
それは、忙しく両手でお料理を持っている歩いている時に、思いっきり勢い良くテーブルの門に足の小指をぶつけました
ぶつかる大きな音がしてお客様が「大丈夫ですかっ!?」とお声かけてくれました
九代目は笑顔で「大丈夫です!!」
本当は、目の前に星が飛んだのですが……
そこはプロですから決して料理は落としません
何事もなかったように笑顔で料理の説明をします
御座敷を出た後に私は廊下で倒れました…笑

次の日に病院に行ったら…
整形の先生がレントンゲンの画像見て
「骨にヒビてますねっ!」
ガ〰️〰️〰️〰️ン
プロって忙しいだろうが…痛いだろうが…
お客様の前では弱音見せちゃダメですから!!
九代目
九代目に惨事が起こりました!
それは、忙しく両手でお料理を持っている歩いている時に、思いっきり勢い良くテーブルの門に足の小指をぶつけました
ぶつかる大きな音がしてお客様が「大丈夫ですかっ!?」とお声かけてくれました
九代目は笑顔で「大丈夫です!!」
本当は、目の前に星が飛んだのですが……
そこはプロですから決して料理は落としません
何事もなかったように笑顔で料理の説明をします
御座敷を出た後に私は廊下で倒れました…笑

次の日に病院に行ったら…
整形の先生がレントンゲンの画像見て
「骨にヒビてますねっ!」
ガ〰️〰️〰️〰️ン
プロって忙しいだろうが…痛いだろうが…
お客様の前では弱音見せちゃダメですから!!
九代目
2020年02月13日
春の菜花!
里山に菜の花、露地ブロッコリー、つぼみ菜と春の到来を告げる菜花数種類が芽吹きます。

「菜花と生湯葉の山葵合え」
旬の各菜花を茹でて、水ぽくならないように水に落とさずザルにあげ、丘上げして冷まします。
菜花をボールに入れて、擦りたての本山葵のすりおろしとお出汁と淡口正油と柑橘絞り汁各少々で合えます。
器に菜花を盛り付け、生湯葉と本山葵をたっぷりと乗せてポン酢醤油を垂らます。
料理がシンプルなだけに、食材は露地の菜花と良質の生湯葉を厳選します。
菜花の甘味とほろ苦さが、畑の肉である生湯葉の濃厚なコクと相まって美味しいです。
本山葵の辛さと香りが菜花と生湯葉の素材を引き立てます。
盛り付けた料理の景色は、畑の菜花に残雪が被ってっているような里山の初春の情景が想い浮かぶような感じのはないでしょうか?
里山懐石らしく、里山の情景が器の中に表現出来た料理になったと思います!!
九代目

「菜花と生湯葉の山葵合え」
旬の各菜花を茹でて、水ぽくならないように水に落とさずザルにあげ、丘上げして冷まします。
菜花をボールに入れて、擦りたての本山葵のすりおろしとお出汁と淡口正油と柑橘絞り汁各少々で合えます。
器に菜花を盛り付け、生湯葉と本山葵をたっぷりと乗せてポン酢醤油を垂らます。
料理がシンプルなだけに、食材は露地の菜花と良質の生湯葉を厳選します。
菜花の甘味とほろ苦さが、畑の肉である生湯葉の濃厚なコクと相まって美味しいです。
本山葵の辛さと香りが菜花と生湯葉の素材を引き立てます。
盛り付けた料理の景色は、畑の菜花に残雪が被ってっているような里山の初春の情景が想い浮かぶような感じのはないでしょうか?
里山懐石らしく、里山の情景が器の中に表現出来た料理になったと思います!!
九代目
2020年02月09日
殻付き牡蠣と露地水菜!

「気仙沼唐桑牡蠣の唐揚げ 露地水菜のせ」
寒風の中で育った露地の水菜の力強さが写真から感じられるでしょうか?
唐桑の綺麗な海で育った牡蠣は、綺麗で濃厚な味わいです。正に海のミルク!
春の産卵に向けて2月に旨味が増した殻付き牡蠣を高温の油でさっとだけ揚げます。
盛り付けは、牡蠣の上に紅葉おろしを忍ばせて、里山の寒風にさらされて甘味の増した露地の水菜と曲がり葱の針野菜をタップリとのせます!
最後に自家製の熟成ポン酢を回し掛けます。
露地の水菜の甘辛い力強い風味が牡蠣の旨味と相まって引き立て合い、とても美味しいです。
露地の水菜は、決して牡蠣の風味に負けないぐらいの存在感を持っています。
冬の露地野菜の凄みを実感出来ます!
冬の里山懐石の真実が見えて来ました!!!
九代目
2020年02月09日
鱈の昆布締め!

「タラの昆布締めと寒ちぢみ雪菜」

1月から2月の始めにかけて三陸では、活朝締めの鱈が入荷します。
鮮度の良いものにひと塩して昆布を当てて更に重しをかけて水分を抜きますと持ち味が生きます。
霜の掛かった寒ちぢみ雪菜も甘味が増して鱈に負けない位の甘味有ります。
あしらいには、桂島の1番積みの海苔と山ウドです。
鱈の旨味を引き立てるのに柑橘系の加減正油を掛けます。
海と里が織り成す旨味のコラボです!
里山懐石の世界!!
九代目
2020年02月01日
原木椎茸!

原木椎茸
県南で育てられた原木椎茸は、菌床栽培と違い、身が、ぎゅーとしまっていて香りも風味もふくよかです。
良質の食材なので、シンプルに炭火焼きで提供します。

「原木椎茸炭火焼」
炭火で焼いた後に、正油と酒を合わせたタレを付けて焼き上げます。
信楽焼の木葉皿に盛ります。
とても茲味深く力強い味わいですよ!!!
九代目
2020年02月01日
露地の寒ちぢみ法蓮草!

「数の子と露地法蓮草の浸し」
生産性の高い過保護なハウス栽培ではなく、冬の寒風や霜の中で精一杯に生きている野菜の甘味を充分に感じれる献立だと思います。
シンプルな料理だけど冬野菜の凄み感じる料理だと思います!
命の一番出汁と振り柚子の香りと共に里山の情景感じてもらいたいです。
九代目